筋骨格系の機能解剖学から捉える
分娩の進行セミナーpolicy&FAQ
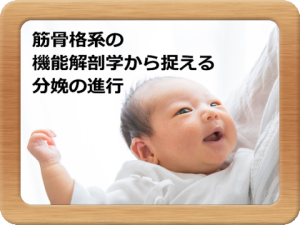
講義概要
分娩介助の現場では、「なぜ分娩が進まないのか?」「なぜこの姿勢が効いたのか?」といった疑問が、日々助産師の皆さんの前に立ちはだかっているのではないでしょうか。
本講義では、そうした現場での“問い”に対して、「筋骨格系の機能解剖学」という新たな視点から解説していきます。
分娩は、単に子宮が収縮して赤ちゃんが下りてくるという単純な現象ではなく、母体の骨盤の形状、仙腸関節や恥骨結合の可動性、筋肉の働き、そして呼吸と腹圧の連動など、きわめて複雑な身体構造の相互作用によって進行しています。
しかし、これまでの助産ケアの現場では、こうした「筋骨格系の構造や機能」に着目した教育や実践は、あまり重視されてきませんでした。そのため、現場で直面する「なぜ進まないのか」「なぜこの体位で進んだのか」といった疑問に対し、経験や勘に頼って対応せざるを得ない場面も多かったのではないでしょうか。
この講義では、身体の構造を知り、機能を理解することで、これらの疑問に論理的かつ解剖学的な根拠をもって考える力を養います。
「子宮が収縮すれば赤ちゃんは生まれる」という認識を超えて、身体構造の働きを深く理解することで、分娩介助はより的確で安全なものになることと思います。
本講義では、WHO基準のカイロプラクティック教育課程を修了し、大学院での助産教育や助産師会での講義に長年携わってきたカイロプラクター・山口康太先生が分かりやすく丁寧に解説します。
20年以上かけて産前・産後ケアに特化して学びを深めてきた解剖学的な知識と、日々現場で妊産婦さんと向き合っておられる助産師の皆さんの豊富な経験が融合することで、臨床に確かな変化が生まれることでしょう。
皆様のご受講を、心よりお待ちしております。
講師紹介
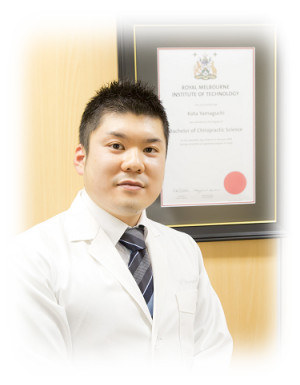
産前産後に特化した治療院
ブルームカイロプラクティック
院長 山口康太
経歴
オーストラリア ビクトリア州立
ロイヤルメルボルン工科大学 健康科学部
カイロプラクティック学科 日本校 卒業
取得資格
Bachelor of Chiropractic Science -Australia-(カイロプラクティック理学士)
Bachelor of Applied Science(Clinical Science) -Australia-(応用理学士)
International Applied Kinesiologist(国際アプライドキネシオロジスト)
International Board Certified Lactation Consultan(国際認定ラクテーション・コンサルタント)
主な講師・講演歴
2015〜2022年
福岡県立大学大学院 看護学研究科 助産実践形成コースにて、「ホリスティック助産学」の非常勤講師
2023年
福岡県助産師会にて、「産前産後のマイナートラブル」に関する講義を担当
2023年
香川母性衛生学会(特別講演)にて、「母乳育児支援」に関する講演
2024年
福岡県助産師会にて、「分娩の進行」に関する講義を担当
2025年〜現在
乳房筋膜リリース協会を通して、助産師向けの講義活動を開始
その他、産婦人科や母乳育児支援団体での講演多数
さらに詳しい講師歴についてはコチラをクリック
講師からのメッセージ
ご受講をお考えの皆さん、こんにちは。
まず初めに、日々、女性と赤ちゃんの命に寄り添い、身体だけでなく心のケアまで担っておられる助産師のみなさまに、感謝の気持ちをお伝えさせてください。
どれほど忙しく、時に困難な状況であっても、産婦さんの声に耳を傾け、温かく励ましておられる姿に、私はいつも胸を打たれています。
妊娠・出産・育児という人生の大きな節目に、そばで寄り添ってくれる存在がいることがどれほど心強く、母親の心の支えになっているか。助産師の皆さまが現場で感じておられる以上に、その存在は多くの方々にとって大きな救いであり、生涯忘れられない出会いとなっているのだと思います。
その一方で、「もっとこうしたいけれど時間がない」「このケアで本当に合っているのか」など、現場ならではの葛藤や迷いを抱えておられる方も少なくないのではないでしょうか。そんな日々のなかでも学び続け、より良いケアを模索しようとする姿勢に、私は心からの敬意を抱いております。
今回の講義が、皆さまの学びや実践のヒントとなり、これからの現場に少しでも活かしていただける内容であれば、これ以上に嬉しいことはありません。何か一つでも「やってみたい」「役に立ちそう」と思っていただけるものが見つかれば幸いです。
私はこれからも、助産師という専門職を心から尊敬し、そして応援し続けてまいります。
カイロプラクターの私が
分娩進行セミナーを行う理由
私は助産師でも医師でもないため、実際に分娩介助を行った経験はありません。そのため、日々現場で「命の誕生」に真摯に向き合っておられる皆さまと比べると、現場のリアルや肌感覚において、どうしても及ばない部分があることを自覚しております。
それでも今回、「分娩の進行」というテーマでお話しさせていただくことにしたのには2つの理由があります。
ひとつは、私はこれまで筋骨格系の機能解剖学や身体運動学の視点から、出産時の骨盤の動きや姿勢について継続的に学び続けてきたことです。産前産後の時期における身体の変化やケアに深く魅了され、その学びに人生を捧げてきたといっても過言ではありません。
ご経験からすでに実感されていることと思いますが、分娩は「子宮の収縮」だけで進行するものではなく、骨盤の動き、筋肉の働き、姿勢による構造の変化など、さまざまな身体的要素の相互作用によって成り立っています。
そのような要素を筋骨格系の視点から分娩を捉え直すことで、現場でのケアやサポートにも新たな気づきが得られるのではないかと考えております。
もうひとつは、助産師の皆さまのご活動に対して、私自身が深い感謝と尊敬の念を抱いており、「少しでもお役に立てる知識をお届けしたい」「日々のケアに活かせる何かをお渡ししたい」という思いを持っていることです。
分娩に直接関わっていないからこそ、俯瞰的に見えることや、他分野の知見と助産ケアをつなぐことができるのではないかと考えております。
機能解剖学や身体運動学からの視点が、何かしら皆さまの実践と重なったり、新たな発見のきっかけとなれば、これ以上に嬉しいことはありません。
もちろん、今回お話しする内容が「現場での正解」や「唯一の答え」であるとは考えておりません。むしろ、実際の臨床現場と照らし合わせた際には、理論との間に差異があるかもしれない、と認識しております。
どうか、皆さまの豊富なご経験と照らし合わせながら、「この体操は使えそうだな」「こういった視点もあるのかもしれない」と、必要な部分を取捨選択していただければ幸いです。
皆さまの助産師としての専門性を最大限に尊重しながら、共に学び合える時間となるよう努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
この講義で学べること
骨盤の動きの理解
骨盤の形状(女性型・男性型)による分娩難易度の違い
仙腸関節・恥骨結合・尾骨の可動性と児頭の下降への影響
骨盤と股関節の動きの連動と分娩の関わり
骨盤の動きから考える分娩促進体操
尖腹とマイナートラブルの関係
呼吸・腹圧・骨盤底筋の連携と娩出力
横隔膜・腹横筋・骨盤底筋の解剖と連動性
腹圧のかけ方・方向と娩出力への影響
「いきむ」動作を解剖学的に理解し、安全に誘導する方法
呼吸と陣痛を利用した胎児の下降促進
分娩進行異常の構造的理解と介入
第1回旋と第2回旋の機序と異常が起きるメカニズム
微弱陣痛・回旋異常・CPD(児頭骨盤不均衡)などの原因
硬膜外麻酔による第2回旋への影響
分娩各期で起こりやすい異常への予防的視点
分娩体位の科学
仰臥位・側臥位・蹲踞位・立位の分娩進行への影響
各分娩期に適した体位とその解剖学的根拠
ピーナツボールやバランスボールの使い方と注意点
硬膜外麻酔時にも適用可能な体位戦略
このような助産師さんにおすすめ
「なぜ分娩が進むのか/進まないのか」を構造的に理解したい方
感覚ではなく、骨盤や筋肉・呼吸の動きといった“見える根拠”で説明できるようになりたい方に。
妊婦さんへの体操指導を、理論的に行いたい方
「なんとなく」ではなく、「この動きがこの関節に作用するから有効」と説明できる視点が身につきます。
進まない分娩・回旋異常などの対応に悩んでいる方
異常の背景にある構造や力学的な要因を理解することで、冷静な判断と安全な介入へのヒントになるかと思います。
無痛分娩時のサポート方法をアップデートしたい方
硬膜外麻酔時でも活用できる姿勢や補助の工夫を、筋骨格系の観点から学べます。
チーム医療の中で、自信をもって発言できる“説明力”を高めたい方
助産師としての専門性を「構造」と「解剖」で裏付けし、医師や他職種との連携を円滑にしたい方にもお勧めです。
分娩支援だけでなく、妊娠中の保健指導・産後の骨盤ケアまで視野に入れたい方
“からだの見方”をさらに深めることで、産前産後の骨盤ケアの質が変わります。
受講料と講義時間について
受講料:55,000円(税込み)
→ 33,000円(税込み)
※現在、期間限定の割引を実施中です。
スライド数360枚以上の分かりやすい講義資料込の料金となっております。
講義資料はPDFにてダウンロードでき、印刷可能です。
講義資料の参考文献はこちら
講義時間:約4時間半
復習しやすいように3部構成になっております。
視聴期限はありませんので、いつでも何度でも見返すことができます。
お申し込み方法
受講のお申込みは下記のURLもしくはQRコードからお申込みください。
準備中です。
受講者の感想
解剖学の視点で分娩を読み解き、今までの経験が言語化できるようになった
「分娩をただの子宮収縮としてではなく、骨盤・関節・筋肉などの構造的視点から理解できたことが大きな収穫でした。今までの“なんとなく”が“なるほど”に変わりました。」
「子宮や胎児の軸の一致、骨盤の可動性など、これまで感覚で行っていた助産ケアの根拠が明確になり、自信を持って説明できるようになりました。」
「回旋異常や分娩停止の背景に、母体の姿勢や関節の動きが関わっているという話に目からウロコ。今すぐ現場で使える知識でした。」
「受講前はカイロプラクターが分娩の講義をするの??と思ってしまいましたが、いざ受講してみるとお産のことをとても勉強されている方なのが分かりました。今までにない視点からお産をとらえることができ、とても興味深い研修でした。」
分かりやすいイラストや動画が充実しており、とても理解しやすかった
「解剖図や3D画像、動画を交えた説明で、筋肉や関節の動きがイメージできました。」
「筋骨格系の知識に苦手意識がありましたが、イラストを通して学べたことで、ぐっと理解が深まりました。」
「分娩中にどんな動きが児の回旋に効果的なのか、実際の動きを交えて説明してもらえてとても納得できました。」
妊娠期からの姿勢・ケアの重要性を再認識
「反り腰や尖腹が、分娩第1期の回旋異常や進行の遅れにつながることを初めて知りました。産前ケアの視点が変わります。」
「“猫のポーズ”がなぜ良いのか、単なる運動ではなく運動学的な根拠があることがわかり、妊婦さんへの説明にも自信が持てそうです。」
「妊娠期からの姿勢づくりが、分娩・産後・育児すべてに影響するというメッセージが強く印象に残りました。」
助産ケアの現場で“すぐ使える”内容
「ピーナツボールの使い方、分娩第1期の過ごし方、分娩時の骨盤の動きなど、明日から現場で活かせる情報が詰まっていました。」
「今までは経験的に伝えていた体操や姿勢も、今回の講義で明確な根拠が得られ、指導に説得力が加わります。」
「保健指導や母親学級で、姿勢や呼吸、体操の意味を解剖学的に伝えられるようになりそうです。」
妊産婦支援に携わるすべての人に届けたい
「助産師だけでなく、妊婦さん自身やその家族、産科医など、分娩に関わるすべての人に知ってほしい内容でした。」
「“また産みたいと思える出産”を支えるために、自分ができることを見直す大きなきっかけになりました。」
「妊娠・出産を“身体の構造”から捉える視点を得られたことで、これからの支援に自信がつきました。」
よくある質問
誰でも受講可能でしょうか?
主に助産師や産婦人科医向けの内容ですが、産前産後ケアに関わっている医療系国家資格(理学療法士など)をお持ちの方にもお勧めの内容となっております。
解剖学に苦手意識があるのですが、大丈夫でしょうか?
筋骨格系に苦手意識を持っている方にこそ、受けてほしい内容となっております。
産科領域ではあまり聞きなれない解剖学用語も出てくるかと思いますが、イラストを豊富に使用して理解しやすいように工夫しております。
分かりやすい講義資料もダウンロード可能ですし、繰り返し視聴していただくことで深く理解できるかと思います。
視聴期限はありますか?
いえ、ありません。いつでも何度でも視聴可能となっております。
リアル開催はないのでしょうか?
以前は開催していましたが、講義時間が長くて消化しきれないのでオンラインセミナーに移行させていただきました。
繰り返し視聴していただくことで、より深く理解できるかと思います。
多くの方からの希望があれば、オンラインセミナー受講者向けの実技講習会も検討しておりますので、乳房筋膜リリース協会のInstagramページのフォローをして最新情報のチェックをお願い致します。